「また言葉がつかえたらどうしよう」
小学生のころ、音読や発表の前になると、いつも不安で胸がいっぱいでした。
私は小学校時代、吃音の悩みを抱えて「ことばと聞こえの教室」に通っていました。
でも、あるトレーニングをコツコツ続けたことで、人前で話すことが徐々に怖くなくなったんです。
今回は、実際に私が教室で行った、4つの吃音トレーニングを紹介します。
どれも自宅で簡単にできる方法なので、お子さんのサポートにもきっと役立ちます。
小学生の私が実践した吃音トレーニング
今日は、私が「ことばと聞こえの教室」で取り組んだ吃音トレーニングの内容をご紹介します。
いずれも専門的な器具や知識は不要で、家庭でも続けやすい方法ばかりです。
※吃音を治療することは難しいとされています。
吃音の症状やトレーニングの効果には個人差があります。
あくまで一例としてお読みください。
① 息を長く保つストロー呼吸・持続発声
最初に取り組んだのは、呼吸を安定させるトレーニングでした。
実際に行った呼吸練習:
- ストローを使って、できるだけ長く息を吐き続ける
- 「ふーっ」と息を安定して吐く練習
- 「あー」と一定の声をゆっくり伸ばす(持続発声)
このような練習を続けることで、息をコントロールする感覚が身についてきました。
呼気が安定すると発声も安定しやすいという感覚がありました。
② 詰まりにくくなる「軟起声」とリズム音読
声の出し方にもコツがあります。
吃音の多くは私のように文の最初で詰まりやすいので、発声のはじめ方を工夫しました。
教室で習ったのは「軟起声(なんきせい)」という方法です。
- 「h、はな」と息に乗せて発音(子音を意識)
- 「ん、はな」など軽い前置きをつける
- 「あー、はな」と息を吐きながら話す(声の立ち上がりをなめらかに)
これに加えて、メトロノームに合わせて読む「リズム音読」も効果的でした。
テンポに乗せて話すことで、詰まりが出にくくなり、安心して読めるようになりました。
メトロノームに合わせて1文字ずつゆっくり読むだけで、詰まりがかなり減りました。
③ 短く・毎日続ける音読練習のコツ
トレーニングを習慣化するために、「毎日ちょっとずつ」「短時間だけ」やるようにしました。
私の練習スケジュール例:
- 息を吐く練習:3分
- 持続発声(あー):3分
- ゆっくり音読:4分
合計で長くても10分。
気分が乗らないときは切り上げる。
短時間でも、継続することで「詰まるかも…」という不安が薄れていったのを覚えています。毎日の習慣として無理なく続けられるようになり、「詰まるかも…」という不安も減ってきました。
④ 詰まっても大丈夫|考え方もトレーニングの一部
教室では、うまく話せなくても先生が急かさずに待ってくれたのが印象的でした。
「大丈夫、少しずつがんばろう」
そう思えたことで、だんだんとスピーチや発表にも前向きに挑戦できるようになりました。
吃音と向き合ううえで、「言葉を詰まらせないこと」よりも、伝えようとする気持ちが大切だと気づかせてもらいました。
まとめ|吃音と向き合うのは「自分のペース」でいい
吃音があると、学校生活で「話す」ことに不安を感じることが多いと思います。
私は不安を抱えていました。
そこで私が小学生の頃にしたトレーニング方法について紹介しました。
私が効果を感じたポイント:
- 呼吸を整える(ストロー・あー)
- 声の出し方を工夫する(軟起声・リズム)
- 短く毎日続ける練習
- 「失敗しても大丈夫」と思える環境
吃音は完全に治せるものではないけれど、「どう付き合うか」は自分で選べます。
吃音に対して少しでも前向きに捉えて、過ごしていってほしいと思っています。
これらのトレーニングや体験談が、同じように悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
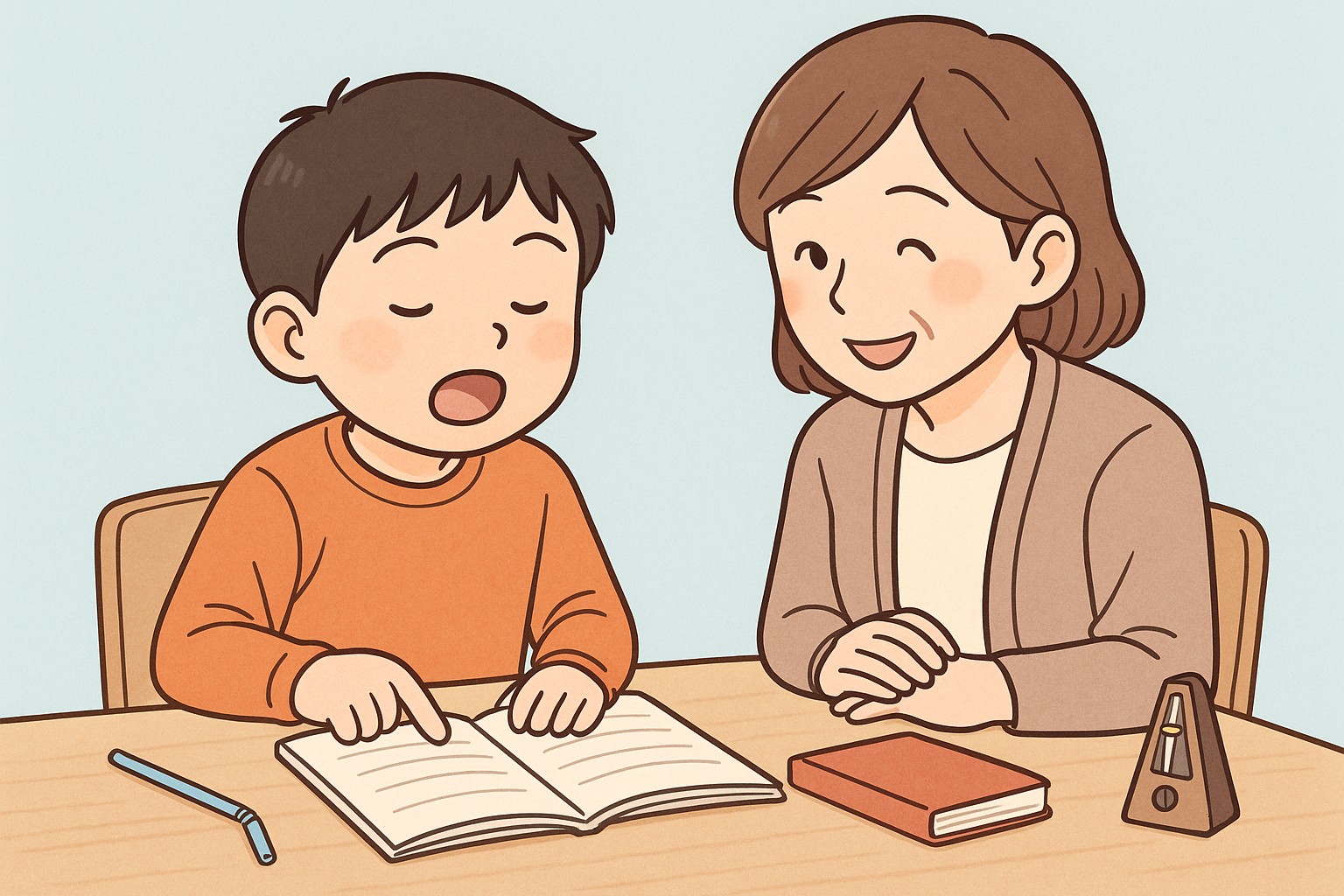


コメント