中学のとき、自己紹介で「吃音があります」と伝えたら、同級生に「そういう障害とかは言わない方がいいよ」って言われました。
これは、私が実際に体験した出来事です。
吃音をカミングアウトすること。それは、決して軽いことではありません。けれど、今の私は「言ってよかった」と思っています。
この記事では、吃音を周囲に伝えることの難しさ、そして伝えることの意味について、私の経験をもとにお話しします。
「言わない方がいい」って、どういう意味?
当時はただ、ありのままを話しただけでした。
自己紹介で「吃音があります」と伝えたのは、緊張したときやスピーチの場面で言葉がつかえることがあるから、前もって知っておいてもらいたかったからです。
でも、あるクラスメートが言いました。
「そういうの、自分から言わない方がいいよ。なんか、損するっていうか…」
そのときは少しショックでした。「損する」って何?自分を隠さなきゃいけないの?って。
でも今思えば、その子なりに気をつかってくれたのかもしれません。
「言語障害」という言葉の持つイメージ
「吃音」は、医学的には「言語障害」に分類されます。
でも「障害」という言葉に、ネガティブな印象を持つ人は少なくありません。まして、思春期の中学生にとっては、目立つことや人と違うことは、とても敏感な問題です。
私の吃音は比較的軽度で、日常会話ではほとんど目立ちません。
だから余計に、「言わなければ気づかれないのに、なんでわざわざ言うの?」と感じた人もいたのだと思います。
でも私は、言わなければ分からないことがあることも知ってほしかった。
カミングアウトには“タイミング”がある
吃音について話すかどうかは、相手との関係性にもよります。
たとえば、初対面の人や一度きりの関係の人に、いきなり話す必要はないかもしれません。
でも、長く付き合っていく人、大切な友人、職場の同僚などとは、どこかのタイミングで伝えた方が、お互いに楽になる場合もあります。
吃音があることを伝えると、多くの人が「そうだったんだ」と受け入れてくれます。そして、私が言葉に詰まっても、落ち着いて待ってくれるようになります。
吃音を話すことで「理解」が生まれる
吃音は、見た目では分かりにくい“見えない障害”のひとつです。
だからこそ、自分の言葉で説明しなければ、誰にも伝わりません。
自分から吃音のことを話すようになって、気づいたことがあります。
それは、自分の話が他の見えない困りごとを抱える人への理解にもつながるということです。
私が吃音について話すことで、「そんなことがあるんだ」と初めて知る人もいます。そして、「話してくれてありがとう」と言ってくれる人もいます。
自分を守るために、“話すかどうか”を選ぶ
私は、どんなときも吃音をカミングアウトすべきだとは思っていません。
実際に、「今は話さない方が自分を守れる」と感じる場面も、これまでに何度もありました。
大切なのは、誰かに言われたからではなく、
「自分はこうしたい」と思えるタイミングで話すこと。
そんなふうに、自分の吃音について安心して話せる関係性を築けたら、とても心強いことだと思います。
「話す」か「話さない」か。
その判断を自分の意思で決められることが、何よりも大事なのではないかと感じています。
吃音を取り巻く環境も変化しており、
10年ほど前から、吃音は「いじめ防止対策推進法」や「障害者差別解消法」の対象となり、社会も少しずつ理解を深めてきています。
私の学生時代と比べると、吃音開示に対して良い環境に変わってきました。
今では、昔ほどカミングアウトにためらう必要はありません。
むしろ、自分から伝えることで、学校や先生から適切な配慮が受けられたり、周囲との関係性がよくなることもあります。
吃音を開示することに、前向きになれる時代が少しずつ訪れている。
そう実感しています。
まとめ:吃音を話すことで、広がる理解がある
中学時代に「言わない方がいいよ」と言われたとき、私は少し迷いました。
でも今では、「吃音があります」と伝えることが、自分の心を軽くし、相手との信頼を深める一歩になると感じています。
吃音は、恥ずかしいことでも、隠すべきことでもありません。
吃音があるあなたはそのままでよく、むしろ必要なのは適切な周りの支援です。
あなたの周りの環境が、あなたにとって過ごしやすい環境に変わっていくことが大切だと思います。
あなたが吃音と向き合う中で心強い味方が1人でも多く増えることを願っています。


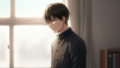
コメント