吃音のある子どもにどう接すればよいのか迷っていませんか?
「どう声をかけたらいい?」「手助けはした方がいいの?」といった悩みを抱える親御さんは少なくありません。
本記事では、吃音当事者の立場から、実際に支えになった親のサポートや逆につらかった対応をもとに、うれしかった接し方を、3つのサポートとして整理して解説します。
吃音と向き合う子どもを支えるヒントを、ぜひ見つけてください。
私が親にしてもらってうれしかった3つのサポート
私が思う3つのサポートとは「待つこと」「受け入れること」「支援すること」です。
吃音が出ても、あわてず“待つ”こと
吃音のある子どもにとって、言葉が詰まる瞬間はとても緊張するもの。
そんなとき、慌てずに待ってくれる親の存在は、安心感そのものでした。
話し終えるまで待ってくれるだけで、「言葉に詰まっても大丈夫なんだ」と感じることができます。
逆に、話を先回りされたり、「こう言いたいんでしょ?」と続きを言われると、自信を失う原因にもなります。
子どもが言葉を言おうとしているときは、ゆっくりした時間と心で“聴く”ことが、何よりのサポートになります。
吃音を「治す」より、「そのままの子ども」を受け入れる
よかれと思って「治そう」とする気持ちが、時にプレッシャーになります。
吃音を「治さなきゃいけないもの」として扱われると、「このままの自分ではだめなんだ」と感じてしまうことも。
吃音が出にくい話し方を学ぶため、言語訓練や専門機関のサポートを受けることも大切です。
でも、それ以上に大切なのは、吃音があってもなくても、あなたは大切な存在だよというメッセージ。
私自身、「吃音があるあなたも、かけがえのない存在」と受け入れてくれた人たちの言葉が、何より力になりました。
支援の場につなげてくれること
子どもが自分の吃音について前向きになれるよう、安心して話せる環境や、同じ悩みを持つ仲間と出会える場に導いてくれることも大きなサポートになります。
私の場合も、親が情報を集めて、吃音の子どもを対象としたグループ活動やことばの教室に連れて行ってくれたことで、
「自分だけじゃない」と感じることができました。
親が一緒に動いてくれることで、子どもは安心して新しい世界に踏み出すことができます。
また学校への働きかけも重要だと思います。
10年ほど前から、吃音は「いじめ防止対策推進法」や「障害者差別解消法」の対象となり、学校での合理的配慮が図られやすくなっています。
学校側へ配慮を促すことでお子さんの学校内での環境が過ごしやすくなると思います。
子どもの気持ちを尊重することが何よりのサポート
吃音の子どもにとって、「自分の話を待ってくれる」「否定せずに受け入れてくれる」そんな親の姿勢は、本当に力になります。
一方で、無意識のうちに「良かれと思って」していることが、子どもを追い詰めてしまうこともあります。
特に注意したいのが、
- 先回りして話の内容を代弁すること
- 無理に「こう話せばスムーズだよ」と矯正しようとすること
こうした対応は、吃音のある子どもにとって「自分を否定された」と感じる原因になりがちです。
まとめ|吃音の子どもにできることは「じっくり待って、受け入れて、寄り添う」こと
吃音があっても、子どもは自分の力で成長し、世界を広げていけます。
親にできることは、そのプロセスを焦らず見守り、信じて寄り添ってあげること。
- 吃音が出ても、話し終えるまで待ってあげる
- 「治す」よりも「そのままを大切にする」
- 学校への働きかけに加えて、必要に応じて、支援の場へつなげてあげる
この3つのサポートが、吃音のある子どもの自己肯定感を大きく育ててくれます。
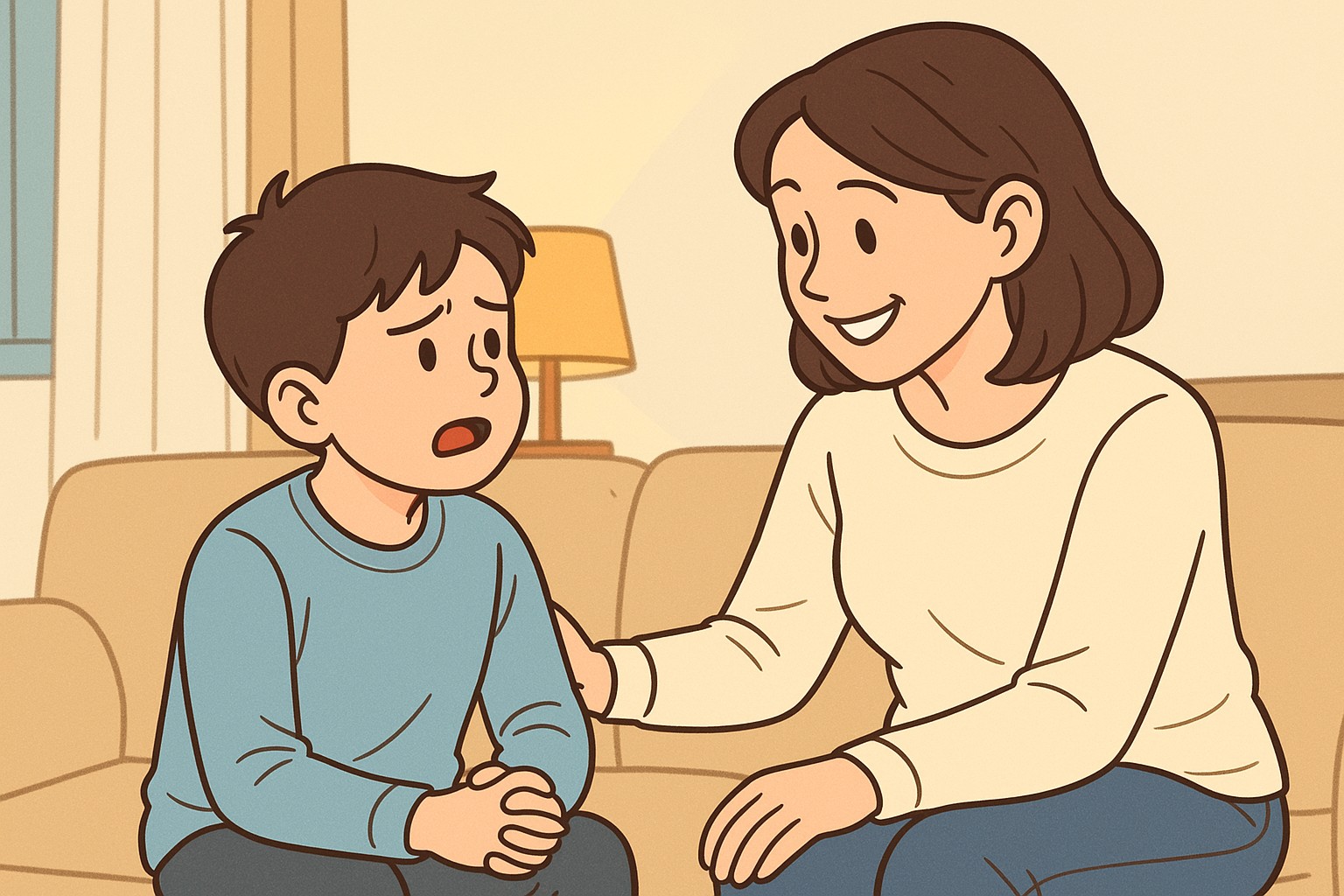


コメント