大学時代、私には大切な友人がいました。
その人には吃音がありました。
話していて、吃音があるなと感じており、タイミングを見て、「俺も吃音を持ってるんだよ」というと、その友人は「ばれたか、ばれないと思ったんだけどな」と吃音を必死に隠そうとしていたことが強く印象に残っています。
その友人は、吃音を「自分の人生にとってマイナスなもの」と捉えていて、「吃音なんてなければよかった」と強く思っていました。
あるとき、彼と将来について話していた時にぽろっとこう言ったのです。
「自分の子どもには吃音を引き継がせたくない。自分の子供が吃音になって苦しむのは嫌だから、子どもは持たないつもりだよ。」
吃音を嫌う気持ち、それも正直な感情
この言葉を聞いて、私は胸がぎゅっと締めつけられるような気持ちになりました。
私は同じく吃音の当事者として、「吃音があるからこそ出会えた人」「吃音があるから気づけたこと」がたくさんあると感じています。でも、友人のように吃音で辛い思いを重ね、傷ついてきた人にとっては、それを「学び」や「意味のある経験」として捉えるのはとても難しく、人生から消し去りたいものなのかもしれません。
吃音に対する感じ方は、本当に人それぞれです。
乗り越えたと感じる人もいれば、乗り越えたふりをして生きている人もいる。
今まさに戦っている人もいます。
だから私は、吃音を「受け入れられないのはダメ」とは全く思いません。
吃音を嫌いだと思う気持ちも、心の中にある正直な思いのひとつですし、私にも昔の嫌な思い出があります。
吃音があるからこそ得た気づきもある
一方で、私は自分の吃音から多くのことを学びました。
- 人の痛みに気づけること。
- 話すことの大切さを誰よりも知っていること。
- 何かを伝えるのに、言葉の流暢さよりも「想い」が大事だということ。
だから私は、自分の子どもがもし吃音だったとしても、一緒に乗り越えていけると思っています。
そして幸いに私は二人の子供に恵まれました。
もちろん不安がゼロだったわけではありません。でも、「吃音がある=不幸」とはどうしても思えませんでした。
「子どもを持つかどうか」は当事者自身が決めること
私の友人は、「吃音の苦しみをわざわざ次の世代に渡したくない」と考えて、子どもを持たない選択をしました。それはとても深く、重い決断だったと思います。
そして私は、「それも一つの選択だ」と思っています。
一方で、私のように「吃音があっても大丈夫」と思い、子どもを持つ人ももちろんいいと思っています。
この問題に、きっと「正解」はありません。
でも、ここで一つだけ強く言いたいことがあります。
「他人が吃音の未来を決める」のは違う
もしも吃音について少し聞きかじっただけの人が、こんなことを言うのは違うと思います。
「吃音って遺伝するんでしょ?だったら子どもは持たない方がいいよ。」
これは、完全に間違った態度です。
吃音が遺伝的な要素を持っていることは事実ですが、それだけで人生の価値を判断することはできません。そして、子どもを持つかどうかを他人が口出しするのは、非常にデリカシーを欠いた行為です。
吃音のある人生が「不幸」かどうかを決めるのは、その人自身だけです。
吃音の「生きづらさ」にこそ社会が向き合うべき
私の友人のように考えてしまう背景には、吃音のある人が生きやすい社会になっていない現状があると思います。
だからこそ必要なのは、「吃音があっても生きやすい社会」を作ることであり、周囲が理解し、合理的配慮をしながら、当事者らしく過ごすことだと思います。
当事者にとって吃音を「隠すべきもの」ではなく、「その人の一部」として自然に受け止められるようになることを目指すべきだと思います。
そうした環境があれば、吃音を理由に人生の選択を狭める必要もなくなっていくはずです。
まとめ:吃音とどう向き合うかは、誰かに決められるものではない
吃音のある友人は私にこれまでとは違った視点を与えてくれました。
そして、教えてくれたのは、「どんな思いも、否定されるべきではない」という学びを得ました。
吃音を受け入れる人も、嫌う人も、そのどちらも間違っていない。
ただ一つ言いたいのは、「吃音だから…」と他人が当事者の行動を決めつけるのは、絶対に間違っているということです。
吃音とどう生きていくか。
それはすべて、本人が決めていいこと。
そして私は、当事者の一人として、誰かの決断を、そっと見守れる人でありたいと思います。

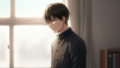

コメント